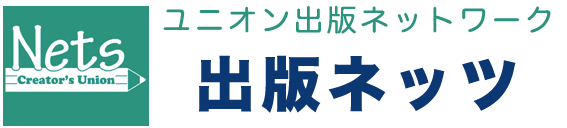喜ばれる鉛筆出し、嫌われる鉛筆出し――校正部会例会 on Zoom
3月7日(月)夜、校正部会例会を開催しました。
テーマは「喜ばれる鉛筆出し、嫌われる鉛筆出し」。校正・校閲、編集、執筆を中心に25名が参加されました。
参加者アンケートに協力してくださった19名のうち16名(84%)が「大いに役立った」、残る3名(16%)が「少しは役立った」と回答。主催者の一員として、大変嬉しく思いました。
というわけで、この例会で参加者の皆さんが学んだことを、以下にご紹介します。
(適宜、補足説明や修正を加えています)
【校正・校閲】
■最優先すべきは誤字・脱字の指摘
- 誤字や脱字の指摘がまず大事であること、過度な統一は避けるべきであることなどです。
- 編集者・Hさんの「100の鉛筆より1つの赤字(誤字の指摘)」、ですよねー!と思った。
- 「どっちでも間違いではない表記に鉛筆入れて、誤植リスクを増やすのはよくない」「校正とは、文字を誤りを見つけること」確かに!
- 編集者など職能側からみての校正者への要望:基本的な文字の見落としの撲滅が最重要、しらみつぶしに指摘するより著者様の意向を尊重する気持ちが大前提、丁寧に見ていることが醸し出されていることも重要←すべて貴重なご意見として活かしていきます
- 校正者は「賢しら」をするな なるほど!! でも、差別とか、他者の立場を考えるように意識すべき。
■用字用語の統一、どうする?
- 用字の統一は校正者に頼るのではなく、編集者がやるべし。耳が痛い話です。正字は必ず指摘しますが、必要かどうか先に聞いたほうがいいのかも、と思いました。(わたしのほうが古い?)
- 世の中ではそんなに統一を望む風潮があるのか……と思いました。
- 校正者・Sさんの「索引に出てくるような用語は統一する」という方針は、分かりやすくてグー。
■ファクトチェック、どうする?
- 編集者のDさんから「指摘のエビデンスとして資料をつけてくれるのは助かる」と伺って、ほっとした。
- 校正者・Wさんの「吉川の歴史事典(国史大辞典?)だけを見てください」という指示が出た話、感服した。「どこまで調べるか」「指摘の根拠として、どの資料を用いるか」ということを指示してくれるよう、こちらからお願いするのもいいかも。
■つまり「正解」は……
- 嫌われるおそれがあっても指摘すべきことは指摘すべし。
- 結局、発注元、媒体などによって違う、正解はわからないということ。
- やっぱり文字校正が基本なんだなーと改めて感じました。余計なえんぴつはいらぬ!それよりは基本に忠実な校正をしてほしい!という編集の方の叫びを胸に刻みました。あとはやっぱりコミュニケーションですね。
■その他、感想など
- 自分が携わった印刷物の発行後、自分自身の指摘箇所を確認するか?:版元からの献本も減り未確認が多くなっている模様(校正者側で留意点ある場合はコピーやメモに残しておく)←参考になりました
- 我流でやって来たようなものなので、他の方のお話はすべて有意義でした。
- 何が校正・校閲の中で大事か、優先順位がわかってきたように思います。
【執筆】
- 冊子内での言葉の統一が必ずしもmustというわけではないこと(法律みたいな出版界の規則かと思っていました)。校正をしてもらう時にも自分で校正をする時にもどんな方針で鉛筆出しをしてもらっているのか、するか、意思疎通が良い作品を作る上で必要だと学びました。
- 正字や統一の考え方などいろいろな意見が聞けてよかった。
【編集】
- 正字を指摘してもらうかどうかは、最初に編集者の側から伝えるべきということを学びました。
- 差別表現やジェンダー不平等を助長するだろうという表現は迷わず指摘するという校正者としての態度と同時に、そういった表現は編集者が原稿整理の段階で指摘すべきという点も尤もと感じました。また、指摘をする場合は学術文献にも準じるレベルで資料を添付するという姿勢にも感銘を受けました。
- 校正者の方々の声を聞くことができてよかったです。
校正部会例会は、2、3か月に1回程度、開催しています。
「参加したい」と思った皆さん、この機会に出版ネッツへの加入をご検討ください。
加入案内はコチラ(中ほどの「加入するには」をご一読ください)。
(瓜谷眞理/校正・執筆/校正部会世話人)
※校正部会
出版ネッツ関東支部の自主活動。校正の仕事をする人たちが中心となって職能の向上や交流を図っています。
校正者以外の人でも、出版ネッツ組合員なら自由に参加できます。